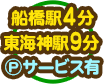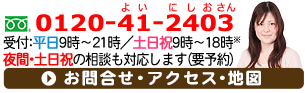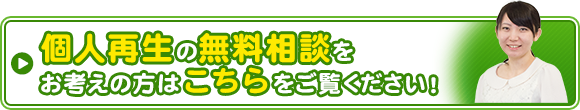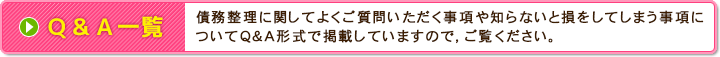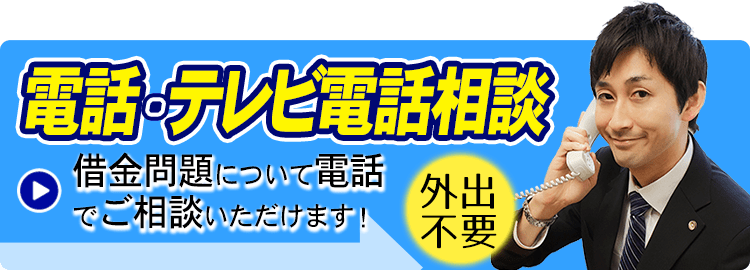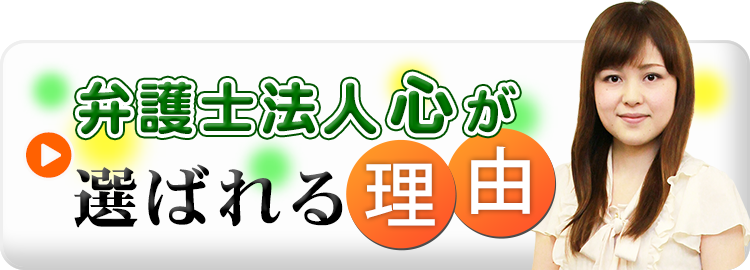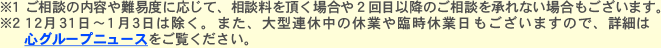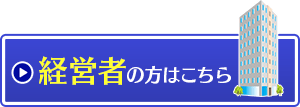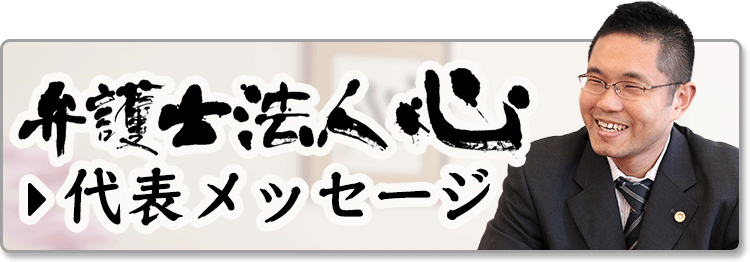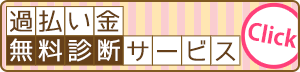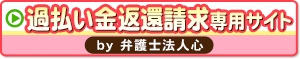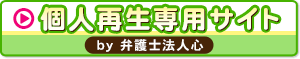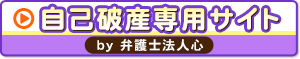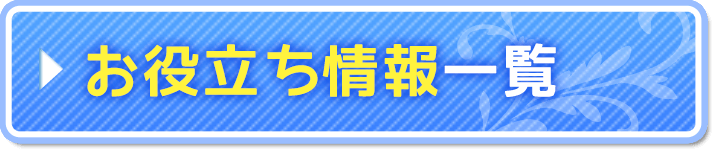「個人再生」に関するお役立ち情報
清算価値保障とは
1 個人再生後に弁済する金額の決定方法
清算価値保障は、債務整理手法の1つである個人再生手続きにおいて登場する概念です。
個人再生は、一般的に、弁済額を大幅に圧縮できる手続きですが、一定の計算方法で求められる金額(基準債権総額)よりも、個人再生手続きを行っている債務者が所有する財産の総額(評価額)の方が大きい場合、当該評価額に相当する金銭を債権者に返済しなければなりません。
この原則を、清算価値保障といいます。
債務者が自己破産を選択したときに債権者に配当される金額を下回ってしまうと、債権者側の保護に欠けるという考えのもとで定められている原則です。
以下、清算価値保障原則について、具体的に説明します。
2 弁済額の計算例
例えば、個人再生をしようとしている債務者の債務総額が400万円あり、解約返戻金の評価額が150万円となる生命保険契約があるとします(単純化のため、他の資産はないとします)。
この場合の、個人再生後の弁済額は次のように計算されます。
まず、基準債権総額で計算した場合の弁済額は、100万円となります。
しかし、債務者は150万円の財産を有しているので、個人再生後に返済すべき金額は100万円ではなく、150万円となります。
3 清算価値保障の原則により弁済額が高額になることもある
清算価値保障の原則のもとでは、債務者の方が所有している財産の評価額が大きいと、弁済額が高額になる可能性があります。
特に影響が大きいのは、自宅不動産です。
すでに住宅ローンを完済している場合や、住宅ローンの残債が少ない場合、自宅不動産の評価額が高額になる傾向にあります。
その結果、個人再生後の弁済額が高額になることがあります。
また、イメージしにくい財産として、退職金請求権があります。
現時点では退職する予定がなかったとしても、見込財産として、職務規定等を基準に計算した退職金の8分の1を、財産の総額に含めます。
勤続年数が長かったり、退職金が高い企業等に勤めていたりする場合、清算価値が高額になり、結果として弁済額が高くなる可能性があります。
所有している財産と個人再生の返済額 個人再生で再生委員がつかないケース